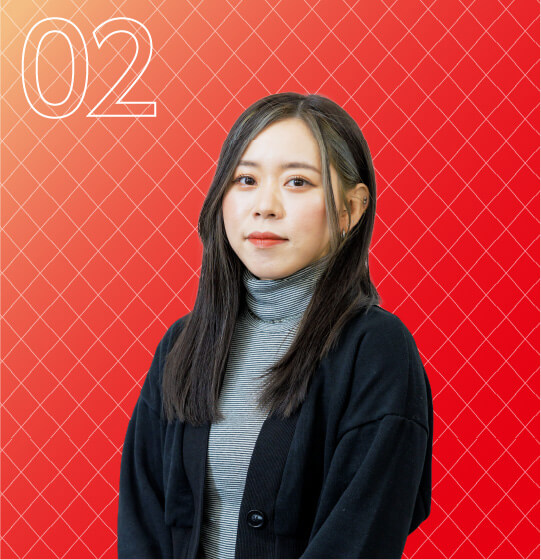シミュレーション技術で、
期待を超える。
DXテクニカルセンター
AI・クラウド開発部
甲村 圭司 KEIJI KOUMURA
1997年入社(新卒)
工学部 生産システム工学科
- ・1997年入社。シミュレーション(CAE)の技術開発業務に従事。
- ・2004年名古屋大学との共同研究(流体分野)を開始。
- ・2008年デトロイトで行われたアメリカの自動車技術会「SAE」にて社外発表。
- ・2012年CAEに関する特許を取得(デンソーテクノ単願出願)。
- ・2014年名古屋大学大学院に3年間通学し、博士号を取得。
- ・2015年機能部に移動し、室長としてテクノ全社のCAE促進活動を推進。
- ・2019年部長に昇格し、VE開発部として更なるCAE技術強化を推進。
デンソーグループに
「VE」を浸透させるために。
大学の研究室で流体シミュレーションを学び、大学の先輩がデンソーテクノで流体解析に携わっていたご縁もあって入社しました。当時はまだデンソーグループでもCAE(Computer Aided
Engineering)が浸透しておらず、デンソーテクノでも数名しかCAEに携わっていなかったため、大学で学んだ知識や経験を活かすことができると考えました。
入社後はCAEの技術開発業務に専念し、2004年からは名古屋大学との共同研究を開始。CAEに関する特許を取得したり、仕事をしながら名古屋大学の大学院に通って博士号を取得したりと、シミュレーションの世界の第一線を走ってきました。
2019年には仮想空間上での設計を推進するVE(バーチャルエンジニアリング)開発部を立ち上げ、CAE技術の研究開発から製品適用、活用支援まで幅広く対応できるような組織運営や人材の育成、しくみ作りなどの環境整備を行っています。
組織のマネジメントを行う一方で、クルマのさらなる静音設計につながる「流体騒音解析」のスペシャリストとして、先端技術の開発や製品適用、CAE結果のレビューなども担当しています。


提供されたデータや
情報をうのみにしない。
若手の頃で興味深かったのが、入社3年目にカーエアコン用ダクトの圧力損失を予測するCAE計算ツール開発を担当したときのエピソードです。
顧客であるデンソーの設計者から風量条件やCAD形状、実験結果を入手し、CAE手法の検討を行ったのですが、合意した目標値の「実験との誤差±10%以内」にはほど遠かったため「このまま使うのは難しい」という状況になったのです。再度、徹底的に実験とCAEの条件の差を絞り込みましたが、解決策が見えません。そこで、何か少しでも解決のヒントが探せないかとデンソー実験部に頼んで実際の試験の様子を見せてもらうことにしました。
すると、なんと実機のダクトが樹脂製だったため大きく変形し、CAD形状と全く異なっていたことが分かったのです。そこで、変形しにくい材料を用いたダクトなら実験との差が±5%程度になる結果を顧客に説明し、CAE結果の信頼を回復することができました。
流体や音の領域は、ほんの少しの環境の違いが結果に大きく影響を与えます。実際にCADの形状と実機の形状が異なることは意外とあることなので、仕事を行う上で提供されたデータや情報をうのみにしてはならないことを学んだ瞬間でした。

想像力を駆使して、最良の提案を。
VE開発部の立ち上げを機に、すでにノウハウを確立することができた定型的なCAE業務は各設計部署に移管しました。そのため、私たちが手がけているのは難易度の高い非定型なCAE業務がほとんどです。
顧客から解析の要望を受けた後、まずは条件やアウトプットなどの具体的な解析仕様を自ら考え、提案していく必要があります。新製品や新しい解析分野の場合、担当者だけでは良いアイデアが浮かばないこともあります。そのため、内部レビューの機会を多く設け、常に誰かとディスカッションしながら解決策を見い出しています。
一方で、解析仕様が決まった後はパソコンと向き合い黙々と作業に没頭している姿も多くみられます。VE開発部は「動」と「静」が混在する特殊な部署のような気がします。
また、複雑な解析を行うことが私たちのミッションの本質ではありません。解析の目的によっては高度な計算が必要ではなく、手計算やExcelレベルでも十分な知見を得ることができます。困っている顧客に対して、コンサルタントとして短い納期でコストを抑えた提案をし、感謝された時は非常に嬉しいです。
1DAY SCHEDULE
出社/メールチェック 会議がつまっているため、メールをためることなく朝に処理する。
会議 大きめの会議が1日2件ほど入っており、空き時間を使ってマネジメント関連業務を行う。
昼食
会議 マネジメント関連の会議に加え、製品のデザインレビューなども行う。
メンバーミーティング 流体騒音シミュレーションのメンバーと進捗を確認し、必要に応じてアドバイス。
退社 子どものために定時で帰ることも。仕事と私生活のバランスはとれている。